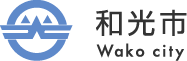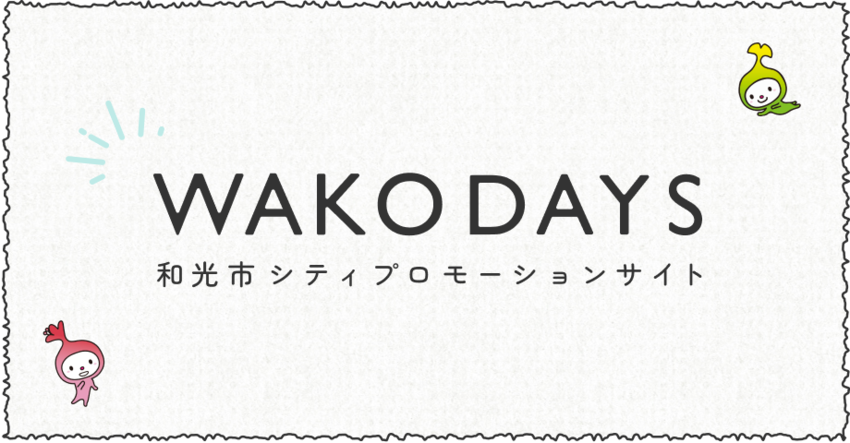介護サービスの利用方法
まずは市区町村で申請をします
本人又は家族が、市役所の長寿あんしん課の窓口で申請をします
法令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、又は地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
必要な書類は
- 要介護・要支援認定申請書(市の窓口にあります)
- 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
- 加入している医療保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 主治医の氏名、医療機関名が分かるもの
申請後交付されるもの
被保険者資格証明書
申請時に介護保険証を提出するため、認定結果通知が届くまでの間介護サービスを利用するときは、介護保険証の代わりになります。
心身の状態を調査します
調査員が自宅を訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います
全国共通の調査票にもとづいて基本調査と概況調査を行います。
基本調査にはこのような項目があります
- 麻痺等の有無
- 清潔
- 関節の動く範囲の制限の有無
- 寝返り
- 薬の内服
- 起き上がり
- 両足がついた状態での座位保持
- 電話の利用
- 両足での体位保持
- 歩行
- 視力
- 移乗
- 移動
- 意思の伝達
- 立ち上がり
- 片足での立位保持
- 理解
- 洗身
- じょくそう(床ずれ)等の有無
- 過去14日間に受けた医療
- 嚥下
- 排尿
- 日中の生活
- 排便
- 食事摂取
- 飲水摂取
- 日常生活自立度
- 衣服着脱
- 聴力
- 外出頻度
- 金銭の管理
- 介護側の指示への反応
- 家族、居住環境、社会参加の状況や変化
- 日常の意思決定
- 行動
概況調査(特記事項)
各項目に該当しなくとも、調査員が特に注意すべきと感じたポイントについて記入します。
どのくらい介護が必要か審査、認定をします
基本調査の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定し、市が認定します。
基本調査の結果
公正な判定を行うため、基本調査の結果をコンピューターに入力して一次判定を行います。
特記事項
基本調査には盛り込めない事項などで調査員が特に重要と感じた点が記載されています。
主治医の意見書
市区町村の依頼により主治医が心身の状態について意見書を作成します。
※主治医がいない場合には、市役所長寿あんしん課又は地域包括支援センターにご相談ください。
介護認定審査会が総合的に審査・判定します(二次判定)
基本調査の結果(一次判定)と特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会がそのくらい介護が必要か(要介護度)や心身の状態が改善されるかどうかを審査・判定します。
市が認定します
介護認定審査会の判定(二次判定)にもとづき、市が要介護度を認定(「要支援1・2」「要介護度1~5」「非該当」)して、本人に通知します。
認定結果の通知が届きます
原則として申請から30日以内に認定結果通知書と介護保険証が届きます。届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
認定結果通知書で確認すること
- 要介護区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
- 認定の有効期間※ など。
※継続して介護サービスを利用する場合は、認定の有効期間(3~24か月)が過ぎる前に更新の申請が必要です。
介護保険証で確認すること
要介護区分、認定の有効期限、支給限度額、介護認定審査会の意見など。
※限度額内でサービスを利用した場合の利用者負担額は1割ですが、限度額を超えるサービス利用の場合は、超えた額のすべてが利用者の負担となります。
介護予防サービス・住宅サービスの支給限度額
|
要介護状態区分 |
心身の状態の例 |
支給限度額 |
|---|---|---|
|
要支援1 |
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 |
50,320円 |
|
要支援2 |
要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 |
105,310円 |
|
要介護1 |
|
167,650円 |
|
要介護2 |
|
197,050円 |
|
要介護3 |
|
270,480円 |
|
要介護4 |
|
309,380円 |
|
要介護5 |
|
362,170円 |
非該当
介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。生活機能が低下している方は介護や支援が必要とならないように市区町村が実施する介護予防事業などに参加できます。
※短期入所サービスの連続した利用日数は30日までとなります。連続して30日を越えない利用であっても、要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないようにします。
ケアプランを作成し、サービスを利用します
要支援1・2の方 介護予防サービスを利用するまでの手続き
ケアプラン作成の依頼
地域包括支援センターなどへ介護保険証を添えて申込み、ケアプランの作成を依頼します。
ケアプランの作成
- 地域包括支援センターなどの担当者が自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査します。
- 調査結果をもとに、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、ケアプランの原案をまとめます。
- 原案をもとに利用者・家族、地域包括支援センターの担当者等で検討を行い、利用者又は家族の同意を得て、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
介護予防サービスの利用
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
※一定期間後に地域包括支援センターの担当者が目標の達成状況を確認します。
利用できるサービスは次のページをご覧ください。
要介護1~5の方 在宅サービスを利用するまでの手続き
ケアプラン作成の依頼
- 居住介護支援事業者を選び介護保険証を添えて依頼します。
- 依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー※)が決まります。
- ケアプランの作成を依頼したことを、市役所長寿あんしん課の窓口に届け出ます。
※ケアマネージャー(介護支援専門員)とは…
利用者に適したケアプランの作成や施設選びなどを行ってくれる幅広い介護知識を持った専門家です。ケアマネジャーは居宅介護支援事業者に所属しています。なお、ケアプランは、自分で作成することもできます。
ケアプランの作成
- ケアマネージャーが本人や家族の要望、心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめます。
- 原案をもとにケアマネージャーが利用者・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
在宅サービスの利用
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
利用できるサービスは次のページをご覧ください。
要介護1~5の方 施設サービスを利用するまでの手続き
介護保険施設と契約
希望する施設を選び直接申込みます。
ケアプランの作成
施設のケアマネージャーが、利用者に適したケアプランを作成します。
施設サービスの利用
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
利用できるサービスは次のページをご覧ください。
地域支援事業のサービス
介護予防事業などが利用できます
和光市の介護予防事業について
和光市では、高齢者の方を要介護状態にさせないための取り組みとして、介護予防スクリーニングなどの結果から、要介護となる介護予防が必要と判断された方などを対象に、お一人おひとりの衰えてきた機能に着目して、そこを強化・改善することで、地域で健康的かつ自立した生活をお送りいただくためのお手伝いをする「介護予防事業」を実施しています。
事業の一例
- うぇるかむ事業
- ヘルス喫茶サロン
- ふれっしゅらいふプログラム
- 管理栄養士の栄養指導
- 3B体操
- 足裏健康体操
- ヘルシーフットプログラム
- フットケアセミナー など
※事業ごとに対象となる方(現在お元気な方、又は特定高齢者)や定員、実施期間が決まっています。長寿あんしん課又は各地域包括支援センターまでお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。