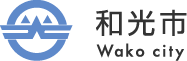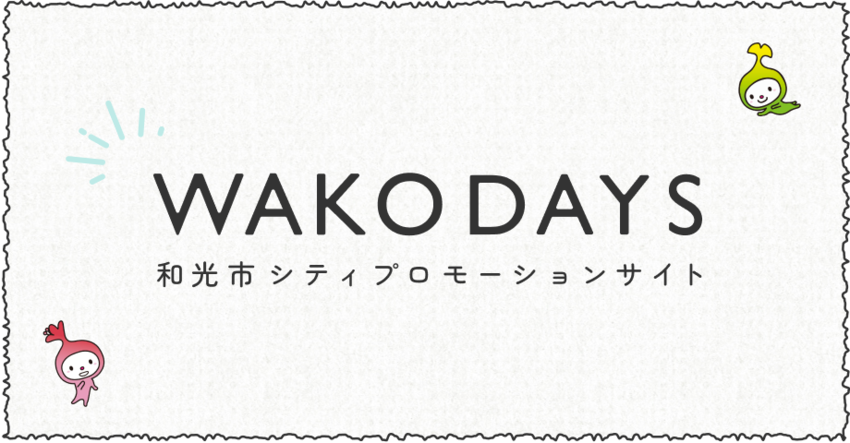税額控除(令和3年度から)
税額控除は、計算された住民税の税額(所得割額)から一定額を差し引くことができる仕組みです。
調整控除
所得税から住民税への税源移譲に伴い納税義務者の税負担が変わらないようにするための措置のひとつとして、住民税と所得税の人的控除額の差を調整する「調整控除」が平成19年度に新設されました。各納税義務者の人的控除の適用状況に応じ、一定の税額が控除されます。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
| 課税所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 |
1、2のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%) |
| 200万円超 |
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%) ※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円 |
※人的控除額に関しては課税課住民税担当までお問い合わせください。
配当控除
配当所得については法人に対し法人税が課税され、更に個人に対しても所得税と住民税が課税されます。その二重課税を調整するため、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。配当控除は総合課税で課税される場合に限り適用され、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。
配当控除額(利益の配当等)
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 1.6% |
1.2% |
| 1,000万円を越える部分 | 0.8% | 0.6% |
配当控除額(公募・私募証券投資信託の収益)
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
| 1,000万円を越える部分 | 0.4% | 0.3% |
配当控除額(一般外貨建等証券投資信託の収益)
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
| 1,000万円を越える部分 | 0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税において控除しきれない額がある場合、住民税の所得割額から控除することができます。控除の適用を受けるためには年末調整時に勤務先に必要書類を提出するか、確定申告が必要です。
次のうちいずれか少ない方の金額が対象となります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(A)×5%又は7%(居住年月日によって異なります。下記の表をご覧ください。)
※(A)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額をさします。
|
居住開始年月日等 |
控除期間 |
控除額 |
|---|---|---|
|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% 【最高97,500円】 |
|
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで 消費税率が8%又は10% |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% 【最高136,500円】 |
|
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで 消費税率が上記以外 |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% 【最高97,500円】 |
|
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで うち、令和元年10月1日から令和2年12月31日 までに入居し、消費税率10%で住宅取得等 した場合※1 |
13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% 【最高136,500円】 |
| 令和4年1月1日から令和5年3月31日まで | 13年 | 所得税の課税総所得金額等の5% 【最高額97,500円】 |
| 令和6年1月1日から令和7年3月31日まで | 10年※2 | 所得税の課税総所得金額等の5% 【最高額97,500円】 |
※1 住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居等の遅延があった場合でも、一定の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措定の対象となります。
※2 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
配当割・株式等譲渡所得割
配当割額控除
上場株式等の配当については、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。
配当所得を申告した場合、下記の通りの順序で配当割の精算を行います。
株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。
株式等譲渡所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、下記の通りの順序で株式等譲渡所得割額の精算を行います。
以下の順序で配当割・株式等譲渡所得割額の精算を行います。
- 住民税所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。
- 住民税均等割額から控除します。
- 未納の市税がある場合、未納税額に充当します。
- 最終的に残った額を還付します。
上記控除を住民税に適用させる場合、住民税に関する納税通知書が送達されるときまでに申告を行わなければ、住民税には反映できません。
寄附金税額控除
地方自治体や一定の団体等に対して寄附金を支払った場合、住民税の税額控除を受けることができます。
寄附金税額控除の内容は、以下のとおりです。
|
対象となる寄附金 |
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)※ |
埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉県支部、埼玉県又は和光市が条例により指定した団体への寄附金 |
|---|---|---|
|
寄附金額の上限 |
総所得金額等の30% | 総所得金額等の30% |
|
基本控除額 |
|
|
|
特例控除額 |
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021) 【調整控除後の市民税・県民税所得割額の2割が限度】 |
なし |
※ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、一定の上限額まで、原則として所得税と住民税から全額が控除されます。
なお、所得税で寄附金控除の適用を受けるためには、ワンストップ特例制度(詳細は下記「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設についてをご覧ください。)の申請をしている場合を除き、確定申告等を行う必要があります。
「ふるさと納税」制度を活用し、東日本大震災、熊本地震等の被災地以外の出身者の方でも復興支援を行うことができます。
「ふるさと納税」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附する場合に、所得税と個人住民税で控除が受けられます。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等になった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、住民税の寄附金税額控除の対象になります。詳しくは、次のページの新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例をご覧ください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設について
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、給与所得者等で確定申告等を行う義務のない方が対象です。ふるさと納税を行う自治体が5以下の場合、当該ふるさと納税を行う自治体(寄附先の自治体)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出を行うことで確定申告等をしなくてもふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる制度です。控除額は、所得税の控除分に相当する額を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。
【申告が必要です。】特例制度の対象にならない方です。
※ふるさと納税についての控除を受けるためには、ふるさと納税に係る寄附金控除も含めて確定申告が必要です。
- ふるさと納税をする自治体が6以上の方
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出した後に転出等で住所地の自治体が変わった方(申請書を提出した自治体に住所変更の届出を提出している場合を除く。)
- 医療費控除等で確定申告、住民税申告等を行う方
※ そのほかの税額控除に関しては課税課住民税担当までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。