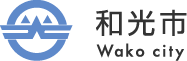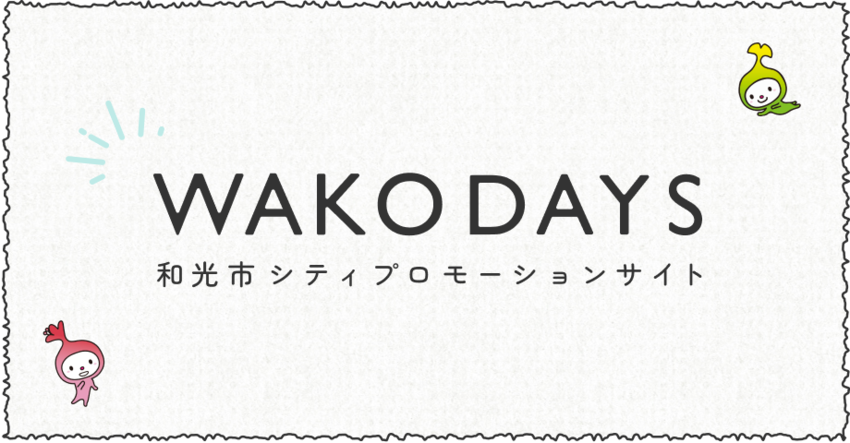令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点
給与所得控除の改正
給与所得控除が見直されます。
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。
なお、子育て世帯や介護世帯に負担が増えないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)
改正後
|
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
|---|---|
| 0~550,999 | 0 |
| 551,000~1,618,999 | 給与収入-550,000 |
| 1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 |
| 1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 |
| 1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 |
| 1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 |
| 1,628,000~1,799,999 | {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×2.4+100,000 |
| 1,800,000~3,599,999 | {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×2.8-80,000 |
| 3,600,000~6,599,999 | {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×3.2-440,000 |
| 6,600,000~8,499,999 | 給与収入×0.9-1,100,000 |
| 8,500,000~ |
給与収入-1,950,000 |
改正前
|
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
|---|---|
| 0~650,999 | 0 |
| 651,000~1,618,999 | 給与収入-650,000 |
| 1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
| 1,620,000~1,621,999 | 970,000 |
| 1,622,000~1,623,999 | 972,000 |
| 1,624,000~1,627,999 | 974,000 |
| 1,628,000~1,799,999 | {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×2.4 |
| 1,800,000~3,599,999 | {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×2.8-180,000 |
| 3,600,000~6,599,999 | {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×3.2-540,000 |
| 6,600,000~9,999,999 | 給与収入×0.9-1,200,000 |
| 10,000,000~ |
給与収入-2,200,000 |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除が見直されます。
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合、控除額が引き下げられます。
なお、給与所得と年金所得の両方ある場合には、片方に係る控除のみが減額されるよう、措置が講じられます(所得金額調控除)
改正後
| 年齢 | 公的年金等の収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 0~3,299,999 | 年金収入-1,100,000 | 年金収入-1,000,000 | 年金収入-900,000 |
| 65歳以上 | 3,300,000~4,099,999 | 年金収入×0.75-275,000 | 年金収入×0.75-175,000 | 年金収入×0.75-75,000 |
| 65歳以上 | 4,100,000~7,699,999 | 年金収入×0.85-685,000 | 年金収入×0.85-585,000 | 年金収入×0.85-485,000 |
| 65歳以上 | 7,700,000~9,999,999 | 年金収入×0.95-1,455,000 | 年金収入×0.95-1,355,000 | 年金収入×0.95-1,255,000 |
| 65歳以上 | 10,000,000以上 | 年金収入-1,955,000 | 年金収入-1,855,000 | 年金収入-1,755,000 |
| 65歳未満 | 0~1,299,999 | 年金収入-600,000 | 年金収入-500,000 | 年金収入-400,000 |
| 65歳未満 | 1,300,000~4,099,999 | 年金収入×0.75-275,000 | 年金収入×0.75-175,000 | 年金収入×0.75-75,000 |
| 65歳未満 | 4,100,000~7,699,999 | 年金収入×0.85-685,000 | 年金収入×0.85-585,000 | 年金収入×0.85-485,000 |
| 65歳未満 | 7,700,000~9,999,999 | 年金収入×0.95-1,455,000 | 年金収入×0.95-1,355,000 | 年金収入×0.95-1,255,000 |
| 65歳未満 | 10,000,000以上 | 年金収入-1,955,000 | 年金収入-1,855,000 | 年金収入-1,755,000 |
改正前
|
年齢 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金に係る雑所得の金額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 0~3,299,999 | 年金収入-1,200,000 |
| 65歳以上 | 3,300,000~4,099,999 | 年金収入×0.75-375,000 |
| 65歳以上 | 4,100,000~7,699,999 | 年金収入×0.85-785,000 |
| 65歳以上 | 7,700,000以上 | 年金収入×0.95-1,555,000 |
| 65歳未満 | 0~1,299,999 | 年金収入-700,000 |
| 65歳未満 | 1,300,000~4,099,999 | 年金収入×0.75-375,000 |
| 65歳未満 | 4,100,000~7,699,999 | 年金収入×0.85-785,000 |
| 65歳未満 | 7,700,000以上 | 年金収入×0.95-1,555,000 |
所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1、給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかの要件を満たす場合
- 特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
※同じ世帯に所得者が2人以上いて、これらの者の扶養親族に該当する人がいる場合、いずれも扶養親族を有することとなります。そのため、共働き世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子どもがいる場合、夫婦双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×0.1
2、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等にかかる雑所得の金額の合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用外となります。
|
合計所得金額 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
| 2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
| 2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
33万円 (所得制限なし) |
| 2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
33万円 (所得制限なし) |
| 2,500万円超 |
0円 |
33万円 (所得制限なし) |
ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男女のひとり親の間の不公平を解消するため、以下のとおり改正されました。
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は適用されません。
- 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親又は寡婦の方は、非課税となります。
改正後
| 配偶関係 本人の合計所得金額 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円以下 |
未婚のひとり親 500万円以下 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
本人が女性 |
同一生計の「子」有り |
30万円 (ひとり親) |
- |
30万円 (ひとり親) |
- |
30万円 (ひとり親) |
| 本人が女性 | 扶養親族:「子以外」有り |
26万円 (寡婦) |
- |
26万円 (寡婦) |
- |
- |
| 本人が女性 | 扶養親族:無し |
26万円 (寡婦) |
- |
- |
- |
- |
|
本人が男性 |
同一生計の「子」有り |
30万円 (ひとり親) |
- |
30万円 (ひとり親) |
- |
30万円 (ひとり親) |
| 本人が男性 | 扶養親族:「子以外」有り |
- |
- |
- |
- |
- |
| 本人が男性 | 扶養親族:無し |
- |
- |
- |
- |
- |
改正前
| 配偶関係 本人の合計所得金額 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
本人が女性 |
扶養親族:「子」有り |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
| 本人が女性 | 扶養親族:「子以外」有り |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
| 本人が女性 | 扶養親族:無し |
26万円 |
- |
- |
- |
|
本人が男性 |
扶養親族:「子」有り |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
| 本人が男性 | 扶養親族:「子以外」有り |
- |
- |
- |
- |
| 本人が男性 | 扶養親族:無し |
- |
- |
- |
- |
所得控除等の適用に係る合計所得金額要件の改正
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等が見直されます。
|
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 | 38万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
| 非課税措置(障害者、未成年、寡婦又はひとり親)の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
| 家内労働者の事業所得等の所得計算の特例 | 55万円以下 | 65万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養控除がいない方 |
45万円 | 35万円 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養控除がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+31万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+21万円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養控除がいない方 |
45万円 | 35万円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養控除がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+42万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円 |
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例
消費税率10%の住宅を取得し、当該住宅を令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に控除期間を13年に延長する措置について、新型コロナウイルス感染症等の影響による入居等の遅延があった場合でも、一定の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに居住の用に供したときにも適用となります。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、住民税の寄附金税額控除の対象となります。対象となるイベントは、主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもののうち、都道府県や市町村が指定したものが対象になります。
対象となるイベント
以下のすべてに該当するイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催又は開催予定のイベント
- 不特定かつ多数の者を対象とするイベント
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたもの
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等あるもの
- 以上の要件に該当し、主催者の申請を受けて文部科学大臣が指定するイベント
※埼玉県と和光市では、文部科学大臣の指定を受けたもの全てを対象とします。
対象年度
上記の対象イベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権の放棄をした場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
- 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。
寄附金税額控除額の計算方法
(寄附金の合計額※-2,000円)×10%
※他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
この制度による優遇の対象になるのは、年間合計20万円までのチケット代金です。
申告方法
イベント主催者から交付された「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告又は市民税・県民税の申告を行ってください。
各証明書の交付方法については、イベント主催者へお問い合わせください。
文部科学大臣が指定したイベントについては、文化庁又はスポーツ庁のホームページにてご確認ください。
療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付が必須となります
令和3年度住民税(令和2年分所得税)の申告から、「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となります。領収書の添付は認められませんのでご注意ください。
平成30年度住民税申告(平成29年分所得税)から医療費控除・医療費控除の特例を申告する際に、領収書の添付が不要(手元で5年間保存)となり、代わりに「医療費控除の細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。経過措置として、令和2年度住民税(令和元年分所得税)までは、医療費の領収書の添付又は提示によることもできましたが、令和3年度住民税から、明細書の添付が必須となります。
明細書は下記よりダウンロードできます。
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。