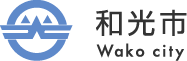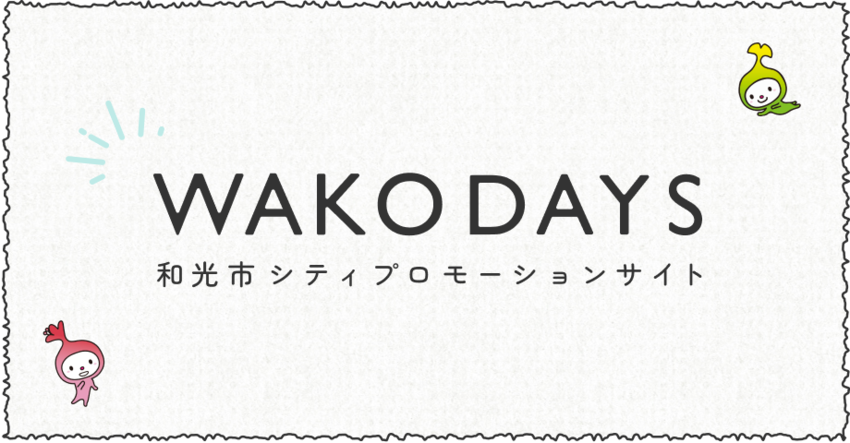「ペダル付原動機付自転車」は適正に利用しましょう
ペダル付原動機付自転車とは
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の排気量又は定格出力を有する原動機を用い、レール又は架線によらないで運転する車(軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。
「ペダル付原動機付自転車」は「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」とは別の乗り物です
「駆動補助機付自転車(いわゆる、電動アシスト自転車)」は、原動機のみで走行する能力はなく、原動機が人の力を補助(アシスト)するもので、道路交通法上は「自転車」に該当します。「型式認定TSマーク」が表示されていれば、電動アシスト自転車の基準を満たしていますので、参考にしてください。
対してペダル付原動機付自転車は、原動機のみで走行することが可能なものを指し、道路交通法上は「原動機付自転車(いわゆる、バイク)」となります。
必要な装置、適用される交通ルールが異なるため、両者は区別しなければなりません。
「ペダル付原動機付自転車」は、運転モードを切り替えても原動機付自転車を「運転」していることに変わりありません
ペダル付原動機付自転車は、原動機を使用せずにペダルを用いて人力のみで走行したり、電動アシスト自転車の運転モードに切り替えて走行したとしても、ペダル付原動機付自転車の本来の使い方に当たることから、原動機付自転車の「運転」に該当します。
原動機付自転車には区分があります
ペダル付原動機付自転車の中で一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当することになり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。
それぞれ、免許の要否、適用される交通ルール等が異なりますのでご注意ください。
交通事故を防止するため、「ペダル付原動機付自転車」の適正利用にご協力をお願いいたします。
「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」、「特定小型原動機付自転車」についての詳細や交通ルールについては、以下の参考リンクをご覧ください。
参考リンク
-
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の型式認定品の推奨について(埼玉県警察HP)(外部リンク)

-
自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう(埼玉県HP)(外部リンク)

-
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HP)(外部リンク)

「ペダル付原動機付自転車」を運転するために必要なこと
「ペダル付原動機付自転車」で、一般原動機付自転車に該当するものを運転するために必要なことは以下のとおりです。
- 一般原動機付自転車を運転することができる免許(原付免許・普通免許等)を受けていること
免許証の携帯が必要です。 - 車道を通行し、原動機付自転車の通行方法によること
歩道は走行できません。原動機付自転車の交通ルールを順守しましょう。 - 乗車用ヘルメットの着用義務があること
必ずヘルメットを着用してください。 - 保安基準を満たした装置を備えていること
道路運送車両の保安基準に適合する制動装置(前後輪)、前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えた車両であることが必要です。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていることが必要です。 - 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること
軽自動車税の納税、標識(ナンバープレート)については、以下のページをご覧ください。
参考リンク
原動機付自転車として必要な基準を満たしていない場合、公道走行はできません。
ペダル付原動機付自転車であることの説明が十分になされずに、販売されるケースがあるため、十分に確認して購入することを心がけましょう。
電動アシスト自転車として販売されていた商品について、独立行政法人国民生活センターが注意喚起を行っていますので参考にしてください。
-
「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-(独立行政法人国民生活センターHP)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
都市整備部 道路安全課 交通安全担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9157 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。