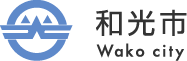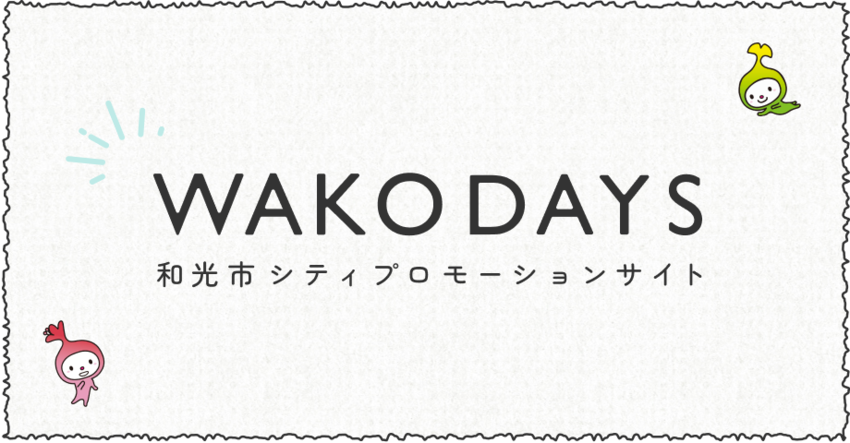わたしたちの健康2025年5月号 糖尿病網膜症
朝霞地区医師会 松岡 雅美
「糖尿病網膜症」とは、糖尿病腎症・神経障害とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、我が国では成人の失明原因の上位です。網膜は眼底にある薄い神経の膜で、物を見るために重要な役割をしていて、光や色を感じる神経細胞が密集し、無数の細かい血管が張り巡らされています。血糖が高い状態が長く続くと、網膜の細い血管は少しずつ損傷を受け、変形したり詰まったりします。血管が詰まると網膜の隅々まで酸素が行き渡らなくなり、網膜が酸欠状態に陥り、その結果として新しい血管(新生血管)を生やして酸素不足を補おうとします。新生血管はもろいために簡単に出血を起こします。また、出血すると網膜にかさぶたのような膜(増殖組織)が張り、これが引きつれて網膜剥離を起こすこともあります(牽引性網膜剥離)。網膜の中心にある黄斑は、物を見るために最も重要な部分です。この付近に、細い血管の壁が盛り上がってできる血管瘤(毛細血管瘤)などが多発したり血液成分が染み出たりして、むくみ(浮腫)を生じると「糖尿病黄斑症」と呼ばれます。これは初期の網膜症の段階でも起こることがあり、視力がかなり低下し、治療は困難を極めます。
積極的な治療法としては、次の3つがあります。
①網膜光凝固術(レーザー)
中等症以上に対して行います。網膜の酸素不足を解消し、新生血管の発生予防や、既に出来てしまった新生血管を減らすことが目的です。光凝固は正常な網膜の一部を犠牲にするので、多くの場合、治療後の視力は不変か、かえって低下し、視界が少し暗く感じることもあります。これは今以上の網膜症の悪化を防ぐための治療であって、決して元の状態に戻すための治療ではありません。しかし、全ての網膜が共倒れになるのを防ぐためにはやむをえないことです。ただし、まれに網膜全体のむくみが軽くなるといったような理由で視力が上がることもあり、早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療です。
②硝子体(しょうしたい)手術
重症の牽引性網膜剥離や硝子体出血が起こった場合に対して行います。眼球に細い手術器具を挿入し、目の中の出血や増殖組織を取り除いたり、剥離した網膜を元に戻したりします。手術がうまくいっても日常生活に必要な視力の回復が得られないこともあり、この時期になると血糖の状態にかかわらず、網膜症は進行していきます。特に年齢が若いほど進行は早い傾向にあるので、厳重な注意が必要です。
③抗VEGF治療(硝子体内注射)
黄斑症の浮腫軽減目的で、その原因物質といわれる「血管内皮増殖因子(VEGF)」の働きを抑える薬剤を眼内に注射し、黄斑浮腫を改善させ、病気の進行を抑制しますが、効果は永続しません。
糖尿病網膜症は、糖尿病になって数年〜10年以上経過して発症するといわれていますが、かなり進行するまで自覚症状がない場合が多く、『まだ見えるから大丈夫』という自己判断はとても危険です。初期の段階での異常、すなわち毛細血管瘤や、小さな出血(点状・斑状出血)、蛋白質(たんぱくしつ)や脂肪が血管から漏れ出た網膜のシミ(硬性白斑)形成等であれば、血糖コントロール次第で治癒も見込めます。
やはり一番大切なことは、基礎疾患の『糖尿病の治療継続』です。そして糖尿病の人は目の症状がなくても定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けることが、生涯に渡り視力を温存する鍵となります。
このページに関するお問い合わせ
和光市役所
〒351-0192 和光市広沢1-5
電話番号:048-464-1111