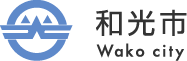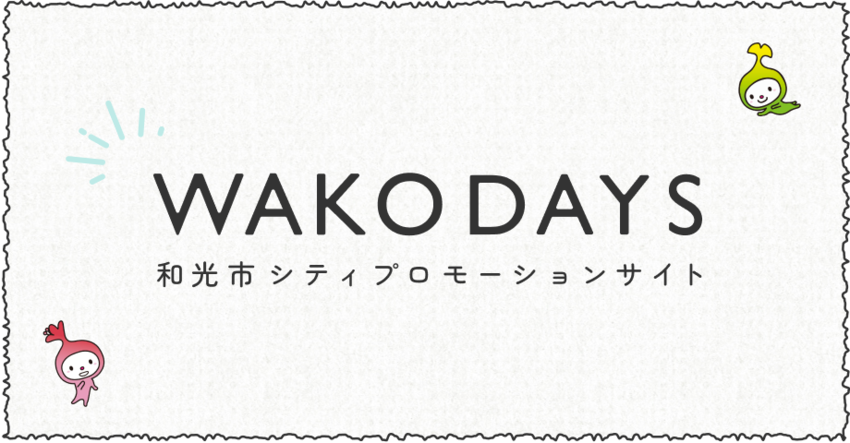和光の野菜
※旬の野菜情報・写真撮影には、和光農産物直売センターの協力を得ました。
じゃがいも

和光市産のじゃがいもは、6月の下旬から収穫が始まります。
新じゃがは、茎や葉がまだ青いうちに収穫した物のことで、皮がとても薄く水分を多く含んでいます。
通常のじゃがいもは冷暗所で保存が利きますが、新じゃがはその水分のため傷みやすくなっています。もし新じゃがを買ったら、できるだけその日の内に食べてしまいましょう。
いんげん

「隠元(いんげん)」という僧侶が日本に持ち込んだ事から名が付いたと言われる夏の豆です。ビタミンB群がとても豊富な緑黄色野菜で、ビタミンBは油に溶けやすいため、油炒めなどがおススメです。
保存が利きづらい野菜で、保存する場合はポリ袋に入れて乾燥を防いだり、サッと茹でて冷凍しておいたりするのが良いでしょう。
玉ねぎ

玉ねぎは、春に植え付けたものを秋に、秋に植え付けたものを初夏に収穫するのが一般的です。通常は収穫後約1か月間、日陰などで風をあてて乾かしますが、収穫のはしりとなる新玉ねぎはすぐ出荷するため、辛味が少なく、タマネギ独特の甘さと香りに加え、みずみずしさと柔らかさがあります。
枝豆

枝豆は、豆と野菜の両方の栄養的特徴を持った緑黄色野菜で、タンパク質・ビタミン・鉄分などが豊富に含まれています。
ビタミンB1は糖質をエネルギーに変え、疲労から来るスタミナ不足の解消に効果があり、また二日酔いを防ぐメチオニンという物質が豊富に含まれています。
バジル

イタリア料理などでお馴染みの香草『バジル』です。
食べ物としてはもちろん、植木としても楽しめます。食べるだけではなく、自らが育てて食べるのもまた面白いですよ。
とうもろこし

朝獲れの特に新鮮なとうもろこしは生でも食べられ、茹でた物よりもシャキシャキした食感とみずみずしさがあり、まるで果物を食べているようです。直売センターでもたくさん出ていますので、ぜひお試しください。(ただし、あまり量を食べるとお腹に悪いので程々に調節しましょう。)
葉とうがらし

小さな鞘(通常のとうがらし)を付けたまま葉ごと出荷するものです。しょう油で煮込んで佃煮にすると美味しく、暑いこの時期にピッタリのおかずになります。
トマト(アイコ)

「アイコ」という品種で、通常の物より甘みと歯ごたえが強く、冷やしてデザートのように食べると美味しいです。
埼玉青大丸ナス

肉質はやや固めでしっとりとした食感です。煮物料理や、青なすの田楽、夏野菜のカレーなどがおススメです。
なすを使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
白菜(若葉)

使いきりサイズとしてとても便利な大きさになっています。葉の根本部分の生長が未熟なため、通常の白菜のシャキシャキ感は劣りますが、青く柔らかい白菜の若葉は一度食べてみる事をおススメします。
レタス

高原レタスなどが晩夏に出るように、涼しくなってくると収穫が始まる野菜です。ここ和光市でも少しずつ出てきました。玉ねぎなど収穫から少し置いて出荷するものとは違い、葉物野菜はとにかく新鮮が美味しい物。収穫して数時間で食べられる和光市産レタスをぜひ食べてみましょう。
秋ナス

初秋に出回る秋ナスは、皮が薄く身が締まっており、種が少ないため切り身の見た目や食感が緻密なのが特徴です。
左の写真では確認しづらいですが、実が大ぶりなので、厚切りにして調理すれば、煮びたしでも炒め物でもたっぷりのボリュームとなるので、ちょっと楽しい一品ができます。
菜の花

菜の花は、栄養価の高い緑黄色野菜で、βカロチンやビタミンB1・B2、カリウム、食物繊維などの豊富な栄養素をバランスよく含んでいます。鉄分も豊富ですので、貧血気味の方にはおススメです。
茹でる食べ方が多いですが、ビタミンCが水に溶け出さないようにサッと茹でるのがコツです。また、カロテンの吸収率を高めるため、油と一緒に調理する炒め物なども美味しいくて良いですよ。
菜の花を使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
ふきのとう

冷たい空気の中で春を思わせる先物としてとても有名な食材。ふきのとうに含まれる「テルペン」という精油成分が喉にとても有効で、ふきのとうを煎じたお茶を飲むと喉の痛みに大変効くそうです。
赤ねぎ

赤ねぎは、葉鞘の軟白部分が赤紫色になる個性的なねぎです。千切りにしてサラダにトッピングすれば色鮮やかでピリリと辛いアクセントになります。また、肉質がとても柔らかく、火を通すと甘味が出ます。特に焼きねぎなどのシンプルな調理方法が一番美味しい食材です。
ねぎ

ねぎにはたくさんの種類があり、代表的なのが「白ねぎ(根深ねぎ)」「葉ねぎ(青ねぎ)」などです。関東では白ねぎ、関西では葉ねぎが好んで消費されます。中部地方では根付近の白い部分と、葉の緑の部分両方を使うそうです。そのため白・緑の部分両方が甘く柔らかい食感の品種も販売されています。
カロテン・ビタミンB2等ミネラルが多く、中でもねぎの辛味成分「硫化アリル」は、ビタミンB1の吸収率アップ、新陳代謝の活性化、利尿や発汗の促進などの効果があります。
八つ頭

里芋の孫にあたる「八つ子」。なぜ孫かというと、親芋があまり生長しないまま周りの子芋が生長すると大きな一つの塊の様にくっついて大きくなります。これが「八つ頭」という子芋です。そして八つ頭から生長した孫が「八つ子」というわけです。
12月~1月に出回る事もあって、子孫繁栄の縁起物として、おせち料理にも使われます。煮崩れしやすいので、皮付きで蒸したり、皮をむいて丸揚げなどで食べるのが良いでしょう。
ほうれん草

冬のほうれん草(七之助)は、霜にあたる事で甘味やビタミンCが増加し、とても美味しいです。その他にカルシウム、鉄、β-カロテンなどの栄養素も豊富に含まれていますが、アクの成分でエグ味の元である「シュウ酸」は、茹でることで除かれます。ほうれん草の他、青菜・山菜類もシュウ酸を含む物が多いので、下茹ですることをおススメします。
ほうれん草を使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
大根

左の黒い大根は辛味が強く、他の大根に比べてホクッと芋の様な食感が加わっています。ちなみに中身は白いです。
右の赤紫色の大根は激辛大根。しかしおろせばとても鮮やかな赤紫色の大根おろしになり、目に楽しい一品が出来ます。
左奥の丸型も中身が赤い品種です。こちらは普通の大根より甘味が強く、歯ごたえも良いため生食に適しています。
このように大根一つとっても様々な種類がありますので、料理に合わせて使ってみてはいかがでしょうか。
大根を使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
白菜

中国では、白菜は大根・豆腐と並び「養生三宝」と言われ精進料理に欠かせない食材です。寒い冬には体を温める食べ物として重宝します。風邪の初期症状は、白菜と豚肉などを合わせた鍋がよく効きます。
白菜はビタミンC、カルシウム、鉄、カロチンなどなど、特に芯の部分に栄養が豊富に含まれています。ビタミンCは熱に弱いので、漬物として非加熱で食べられる白菜はとても便利。乳酸菌と併せてお腹にも優しいです。
人参

和光市は冬にんじんの指定産地となっていて、数多く栽培されています。緑黄色野菜の代表的存在で、βーカロチンの宝庫としても有名です。βーカロチンの効能は、抗酸化作用による老化防止や美肌効果等があります。脂溶性ビタミンなので油で調理する事により吸収率が向上します。また、にんじんの葉は栄養が豊富で、捨てずに食べましょう。茹でてナムルにしたり、かき揚げなどが美味しいです。オーブンで焙って乾かし、細かくして粉パセリの様に使うのはいかがでしょうか。
人参を使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
ブロッコリー

野菜の王様と呼ばれるほど栄養豊富な緑黄色野菜。煮て焼いてなど使用用途がとても多く、食べやすいのも特徴です。
栄養面では、β-カロテンやビタミンB群、ビタミンC・Eを多く含むほか、カルシウムやカリウム、鉄などのミネラル、食物繊維も豊富な野菜です。胃の粘膜を修復する作用が強く、ストレスの多い現代人には欠かせない野菜です。
カリフラワー

カリフラワーはビタミンCが豊富で、熱を加えてもビタミンが壊れづらいという特徴があります。しかしビタミンCは水に溶けやすいので、スープなど茹汁ごと食べる方法が良いでしょう。
また一番ビタミンが多いのが、普段食べてる花蕾(からい)ではなく葉の部分。かき揚げや野菜炒めのちょっとした香り付けついでに使ってみるのも良いかも知れません。
カリフラワーを使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
大根

煮て、焼いて、干して、漬けて良し。日本の代表的な野菜で、世界一消費しているのも日本です。葉や根にはビタミンA・C、カロチン等が含まれています。
「大根役者=あたらない(「役者として売れない」と「食中毒にならない」を掛けた)」という洒落があるほど消化に良い野菜。ちなみに、これは大根に含まれる様々な分解酵素のおかげで、イカやタコと一緒に煮ると肉質が柔らかくなるのは、これらの酵素が働いているからです。
サラダからし菜

サラダ菜のまろやかな甘味と、ワサビの様なスッキリした辛味が特徴です。甘味と辛味が共存した、何ともフシギな味。ぜひお試しを!!
キャベツ

キャベツに多く含まれる栄養であるビタミンU、通称キャベジン。胃炎・胃潰瘍を防止する作用があり、多くの胃腸薬に配合されています。
キャベツの芯には豊富なビタミン類が含まれているので、なるべく捨てずに食べましょう。ビタミンが壊れないように生食がおススメです。
かぶ

春の七草「すずな」としてお馴染みの野菜です。根の白い部分は煮物・漬物等がとても美味しい食材。しかし栄養面では根より葉の方がとても豊富。カルシウム・カロテンを根の5倍近く含み、捨てるには惜しい食材なのです。
一方、根の方は消化酵素であるジアスターゼを多く含んでいます。胃の調子が優れない時にはカブの漬物が効果的です。
里芋

里芋の主成分はデンプン質で、他に食物繊維・ビタミンB等が多めです。
冬瓜

冬瓜の効果は、ダイエット(ほぼゼロカロリー)・利尿効果(昔からむくみとりに用いてきた程)・カゼ等の予防(ビタミンCが非常に豊富)といろいろな嬉しい栄養が含まれています。
そして捨てる所の無い食材。果肉は生で、皮は炒め物に、ワタは煮物・スープの具に。種は難しいですが、古代中国では利尿・解毒薬として使われていたそうで、栄養たっぷりなのです。
小松菜

小松菜は、緑黄色野菜で特にカルシウムが豊富です。ダイエット中の方や日々激しく運動する方にぜひおススメ。
小松菜に含まれるカルシウムが身体の土台となる骨を強化し、その他の豊富なビタミンがタンパク質の吸収を促したり、疲労回復をしたりと、至れり尽くせりな食材だからです。
オクラ

糖質・無機質・ビタミン等を多く含む多栄養食材。ペクチンが粘りの主成分です。ペクチンは整腸作用・血糖値の抑制に役立ちます
ねばりが苦手な方は、酸性の食材と一緒に調理するとねばりが分解されます。
キュウリ

96%が水分のキュウリは、ビタミンB1・C・E・カリウムを多く含んでいますが、その量はさほど多くはありません。
しかし、水分のが多くのカリウムを含んでいるため、体の過剰な塩分を排除し、利尿効果やむくみを解消する効果があります。
ナス

ナスは夏にうれしい野菜です。「クロロゲン酸」というポリフェノールの一種である渋味成分が胃液の分泌を促進する作用があるので、食欲不振になりがちなこの暑い時期にピッタリなのです。ナスには身体を冷ます効果もあるので、秋口に食べるナスには保温効果の高い生姜を添えて食べると良いですよ。
トマト

トマトには「リコピン」と呼ばれる色素が含まれています。この栄養素は抗酸化作用に優れ、若返り効果があると言われていますが、抗酸化作用はトレーニングに疲れた身体を癒す効果もあります。若返り+体力回復効果を、食卓に用意してみてはいかがでしょう?
トマトを使ったレシピは以下の「旬の野菜を使ったレシピ」のページをご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業支援課 農業振興担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。