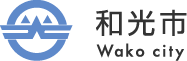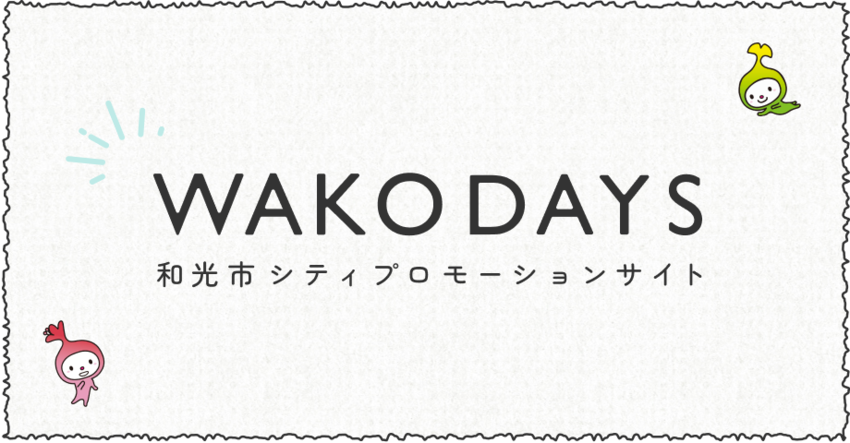令和7年度和光市広島平和記念式典中学生派遣事業報告
広島平和記念式典への参列、平和に関する施設見学や学習プログラムに参加するため、市内の中学生6名が「和光市広島平和記念式典中学生派遣事業」に参加しました。

派遣の目的
和光市は令和5年3月に「平和都市」を宣言しました。日常生活の中で感じられる平和の大切さや、戦争のこと、核兵器を使わないことを、市民の皆さんと一緒に考えながら、いろいろな活動を通して平和への思いを伝えています。
令和7年は、太平洋戦争終結から80年という節目の年にあたります。この機会に改めて平和について考えるため、広島平和記念式典への参列、平和に関する施設見学や学習プログラムへの参加を通して、次代を担う青少年が、平和の尊さや命の大切さについて学び、平和への理解を深めることを目的として実施しました。
主催
和光市
派遣期間
令和7年8月5日(火曜日)から7日(木曜日)まで(2泊3日)
派遣事業参加者
派遣者
第三中学校 3年 丸山 柚妃(団長)
第二中学校 3年 丹野 まい(副団長)
大和中学校 2年 黒田 絢大
大和中学校 2年 栁下 昌輝
第二中学校 1年 針谷 侑和
第三中学校 1年 小髙 楓
引率者
和光市企画部 企画人権課 中川 大
和光市教育委員会事務局 学校教育課 山中 惇太郎
学習目標
- 平和記念式典参列や平和学習プログラムへの参加を通じて、戦争の悲惨さや平和の大切さ、命の尊さへの理解を深め、自分の言葉で語れるようになる
- 学校、地域、家庭等で、派遣で得たものを伝承していく
事業報告書
実施までの流れ
3月17日~4月25日 派遣事業参加者応募(応募者45名)
4月30日~5月12日 派遣参加者選考委員会(書面開催)
5月16日 派遣参加者の決定
6月22日 第1回事前研修会
7月22日 第2回事前研修会、出発式
8月5日~7日 広島市への派遣
派遣スケジュール
8月5日(1日目)
- 平和記念公園碑めぐり
- 広島城・縮景園見学
8月6日(2日目)
- 平和記念式典参列
- 広島平和記念資料館見学
- 「全国平和学習の集い」参加
ユース・ピース・ボランティアによる原爆被害の概要説明
被爆体験講話聴講
グループディスカッション
発表・講評
8月7日(3日目)
宮島・厳島神社見学
平和記念公園碑めぐり
広島駅到着後、平和記念公園に向かい、ボランティアガイドの方の案内のもと、原爆ドームをはじめとした、様々な慰霊碑や記念碑を見学しました。
一つ一つの施設や碑について、自身が被爆者であるガイドの方の話に生徒たちは真剣に耳を傾けながら、熱心にメモを取っていました。特に印象に残ったのは「被爆した墓石(慈仙寺跡の墓石)」という碑です。当時爆心地から約200mの距離にあったお寺は、一つの大きな墓石を残して全て吹き飛ばされました。残った墓石の周辺だけ、窪地になっていますが、それは、平和記念公園が盛土して建設されたためであり、公園の下には、まだいくつもの遺骨が眠っているかもしれないとの説明がありました。
これらの碑めぐりを通して、多くの無実の市民が犠牲になった事実を直接肌で感じることにより、翌日に参加予定の「平和記念式典」や「平和学習の集い」に臨む決意を新たにしていました。




全国平和学習の集い
「全国平和学習の集い」では、まずユース・ピース・ボランティアの方から原爆被害の概要について説明を受け、次に被爆者の方からの体験講話を聴きました。実際の体験に基づいた話は心に深く響き、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて実感しました。
続いて行われたグループディスカッションでは、全国の生徒たちと共に、各自の地元での戦争被害や、現代の平和でない状況について意見を交わしました。それぞれのグループが発表を行い、講評を受けたことで、平和について多角的に考えることができました。



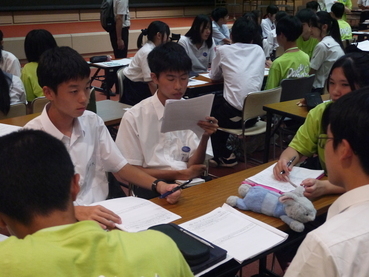

参加者感想(作文)
第三中学校 3年 丸山 柚妃(団長)
戦争で命を落とした親族の存在を知り、戦争をより身近に感じるようになった私は、いつか広島を訪れて戦争について学びたいと思っていた。市の平和記念式典派遣事業に参加し、原爆投下から八十年を迎える今年の八月六日、私は広島の地に立った。
原爆資料館では、目を背けたくなるような写真や展示物が数多く並んでいた。胸が締めつけられるような苦しさを感じながら、それでも私は写真から目をそらさず、無言で訴えかけてくる悲しみと向き合った。犠牲者十四万人という「数字」は、これまで頭で理解していたつもりだった。しかし、資料館で目にした数十人の遺体の写真だけでも地獄のような光景で、その数の重みと現実に私は言葉を失った。「戦争の痛ましさ、核兵器の恐ろしさ、そしてこの無念をどうか忘れないでほしい」という願いが静かに私の心に届いてきた。
平和の集いでは、九十四歳の河野キヨ美さんの被爆体験を聞かせいただいた。今の私と同じ歳の十四歳で被爆された河野さんは、八十年が経った今でも、あの夏の広島の光景を忘れられないと語っていた。その辛い記憶を「生き残った者の責務」として語り続ける姿に、私は深く心を打たれた。河野さんのお話を伺い、今ここで感じたことを私も一人でも多くの人に伝える義務があると感じた。私たちが当たり前に送っている今の平和な日常は、多くの犠牲の上に成り立っていることを忘れてはならない。
広島の体験の中で、特に印象的な言葉がある。それは「一人の百歩より、百人の一歩」だ。私はまず、友達や家族に広島での体験を伝える事で、自分なりの一歩を踏み出そうと思う。若者が平和を考えることこそが未来への希望なのだと思う。争いを繰り返さない為に多くの人が戦争や原爆という負の体験について知り、次の世代へ伝える事が大切だ。広島で感じ、学んだ事を心に留め、平和の大切さを伝えていく存在でありたいと思う。
第二中学校 3年 丹野 まい(副団長)
このたびは派遣事業に参加させていただき、誠にありがとうございました。
平和記念式典では黙祷を捧げると、原爆で命を落とした方々の無念や、残された人々の深い悲しみが胸に迫り、これまで教科書で学んできた知識が現実の出来事として強く実感させられました。
その後に訪れた原爆資料館では、被爆当時の写真や遺品を目にしました。焼け焦げた衣服や壊れた日用品は、そこで確かに暮らしていた人々の存在を物語っており、一つ一つの展示から「突然奪われた日常」の痛みが伝わってきました。特に、小さい子が乗っていた三輪車を見たとき、未来を夢見ていたはずの命が一瞬で絶たれた現実に心が震え、戦争の悲惨さを改めて思い知らされました。
午後には広島市役所で全国の自治体の方々と平和について語り合い、さらに被爆者の証言を直接伺う機会を得ました。
被爆者の方は、「当たり前だと思っている今の平和や暮らしは、多くの人々の犠牲の上にあることを、若い人たちに考えてほしい」とおっしゃっていました。そして「世界情勢は不安定だが、希望を失わず、若い人々に核廃絶と平和への願いを、時間が許す限り訴え続けたい。それが、あの夏の日を生き残った者の責務だ」と強い言葉で語られました。
派遣後、私はこの経験を両親や友人、そして先生方にも伝えてきました。広島で見聞きしたことを話す中で、周囲の人々も改めて平和の大切さを考えてくださり、とても嬉しかったです。平和の基盤には過去の苦しみや犠牲があることを知り、今の暮らしが決して当然のものではないと学びました。だからこそ、私たち若い世代がその歴史を忘れず、語り継いでいくことが大切だと思います。それが、次世代を担う私たちの役割だと考えます。
広島での体験は、平和は決して当たり前ではなく、守り続ける努力によって成り立つものだと教えてくれました。今回の学びを原点として、これからも平和を意識し、語り継ぎ、伝えていける人間でありたいと強く思っています。最後になりますが、このような貴重な機会を与えていただいたことに、心より感謝申し上げます。
大和中学校 2年 黒田 絢大
私は広島の平和記念式典に参加し、実際に現地で平和について考えることができました。会場では多くの人が集まり、原爆で亡くなった方々を追悼していました。特に印象に残ったのは、黙祷の時間です。会場全体が静かになり、多くの人の思いを一体となって感じることができました。この体験を通して、戦争や原爆の悲惨さを身近なものとして感じることができました。
また、被爆者の方から直接体験を聞く機会もありました。家族が一瞬で失われたというお話はとても重く、戦争によって人々の生活が奪われてしまったことを強く実感しました。これまで戦争についてはあまり学ぶことがなかったのですが、今回の体験を通じて「過去の出来事」ではなく「未来につなげなければならないこと」だという意識が生まれました。私の考え方も、「平和は当たり前のものではなく、自分たちが守り続けるもの」というものに変わりました。
派遣事業を通じて学んだことは、平和とは単に戦争がない状態ではなく、互いを思いやり尊重しながら生活できることだという点です。今後は、今回得た学びを周囲に伝えていくことが重要だと思います。例えば、学校での発表や友人との会話、家族との話し合いの中で、今回感じたことを共有していきたいです。小さな取り組みでも、次の世代へと語り継ぐことの第一歩になると思います。
今回の参加を通して得た経験は、自分にとって貴重な学びとなりました。これからも平和の大切さを意識しながら生活し、その思いを周囲に広めていきたいと思います。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。
大和中学校 2年 栁下 昌輝
僕は平和記念式典派遣事業に参加し、戦争で日本にどのような事が起きたのか、広島の地でどのような悲惨な事が起こったのかを学んだ。その体験や経験の中で印象に残っている事が四つある。
一つ目は平和記念式典だ。式典には八十年前に原爆が落とされた広島に日本国内のみならず、世界中の国から様々な人が集まっていた。改めて、原爆は世界へ平和の重要さを伝えていると実感した。
二つ目は原爆ドームや平和記念資料館を見学した事だ。初めて見学した僕は、原爆によってどのような被害が出たのか、言葉だけでなく自分の目で見て感じることが出来た。
どれも想像を超えた展示内容で、原爆の威力の大きさを改めて感じた。また罪のない人々が残酷な形で命を奪われた事がとてもショックだった。こんなことは日本ではもちろん、世界中のどこであっても繰り返されてはならないと強く思った。
三つ目は、平和学習会の中で行ったグループディスカッションだ。全国様々な地域から集まった人たちと、それぞれの地域でどのような被害があったのかを発表しあった。これまで僕は戦争被害といえば一番に広島が思い浮かんでいたが、戦争での被害は広島だけではなくたくさんの地域で様々な被害があったと知った。そして平和とは「争いがないこと」だけでなく更に「世界中の人が嫌な思いをせずに過ごせること。」なのではないのかと思った。
四つ目は、被爆者の河野キヨ美さんの話をうかがったことだ。僕は被爆者の方の話をうかがうのは初めてだったが、当時の大変さやつらさが本や資料で見るより何倍も迫力があるように感じた。同時に、実際に戦争を体験した方から直接お話を聞ける最後の世代としての責任も感じた。
その責任を果たすためには、今回学んだことをしっかりと後世に伝えていかなければならない。
見聞きした戦争の記録は繰り返し伝え続けなければならないと思う。このような報告書の作成、冊子等にまとめて図書館等で誰もが閲覧できるようにする、SNSなどを使いより多くの人達に伝える等の工夫が必要だ。時には友達同士で意見を交換し合って戦争の話題を身近なものにすることも大事だと思った。
次の世代を担う者としてあらゆる方法を尽くし、二度と争いを繰り返さないと僕は胸に刻んだ。
第二中学校 1年 針谷 侑和
知りたい―応募作文で強調させたこの言葉は、事前学習から派遣を終えるまで僕の根幹になった気がする。派遣では、見て、聞いて、感じて、様々な感覚で知ることができた。原爆資料館では、被爆されて亡くなった方々の遺品や、熱線で溶けてしまったガラスなど、事前学習で学んできたからこそより深く感じる恐怖を目の当たりにした。
資料館を回っていて遺品の服が展示されている所を歩いていた時、ふと疑問に思った事がある。僕たちと同じ中学生の服なのに、今の僕たちの服より明らかにサイズが小さいのだ。ほかの年代の方の服も見てみると、それらも今より小さい。戦争中は食量も配給で今より食べ物が少なかった、という話を聞いたことがある。だから当時の人々は痩せていて、服も今より小さかったのかもしれない。そう思うと、胸が苦しくなる。現代は当たり前にご飯を食べられるし、当時の生活よりずっと良い生活ができている。それを当たり前と思わずに、普段の当たり前に感謝して生活することが大切だと思った。これまでは『原爆は一瞬にして沢山の命を奪ってしまった』と大きく捉えていただけだったが、実際に資料館に行って、原爆で亡くなった方々一人ひとりの人生が垣間見えた。
派遣を通じて、『本当の平和』とは、戦争や争いがないことはもちろん、皆が安心して暮らせる日常のことだと実感した。みなさんは、平和を他人事として考えていないだろうか?当時の状況に目を背けずに、自分事として捉え、理解し、伝えていくことで平和を作ることができると思う。まずは身近な人からでもいいから、しっかりと伝えていこうと思った。
広島平和記念式典に参列して、会場にいる人も、いない人も、この時間に多くの人の平和への祈りがこの会場に集められていることに気づいて、僕は感動した。本当の平和の尊さを感じた気がした。僕の名前は「侑和」だ。「和」は、平和の和から名付けられた。ちなみに弟の名前は「倫平」で、「平」は平和の平だ。二人で平和を作っていってほしいという願いが込められている。その期待に応えようと思う。
このような貴重な経験をさせて下さった多くの方々には感謝の気持ちでいっぱいだ。これからは、この経験を生かして生きていきたいと思う。
第三中学校 1年 小髙 楓
「当たり前だと思っている今の平和な暮らしが多くの人々の犠牲の上にあることを若い人たちに考えてほしい」
これは、当時14歳で被爆し、今回の派遣事業でお話を伺った河野キヨ美さんの言葉です。
1945年8月6日。今からちょうど80年前のことです。世界で初めてとなる原子爆弾の爆風や熱線が、凄まじい音と共に広島の街と人々の人生と当たり前の生活を一瞬にして奪いました。爆心地近くにいた人は皮膚がはがれて性別も分からなくなり、「水がほしい」と泣き叫び、眼球や舌や内臓が飛び出し、亡くなった人が山のように積み重なっていたそうです。
私はテレビの報道や学校の授業でしか戦争や平和について考えたことがなく、戦争とは大勢の命を奪ってしまうものだという漠然としたイメージしかありませんでした。今回、被爆者の方から耳をふさぎたくなるような辛い体験談を聞いたことで戦争の悲惨さを肌で感じる事ができました。そして、戦争が終わっても一生消えることのない傷跡や放射能の恐怖や偏見に苦しむ多くの人がいるということを知りました。思い出すことも辛いはずなのに話してくださる被爆者の方の思いを受け止め、その声を語り継いでいく使命を感じました。
また、私は今まで勉強をすることが面倒くさいと感じることがありましたが、一生懸命勉強をしたり、気軽に本を読んだり、お腹いっぱいに食べるという私にとっては当たり前の事が当時は出来なかったという事実を目の当たりにし、それができることを「有り難い」と思うようになりました。そして今、私がここに立っていること自体がとてもすごいことなのだと気づきました。
本当の平和とは、多くの犠牲の上にこの生活ができていることを心に留めながら今の日本のように当たり前の生活をするという単純そうで全く単純ではないものなのです。それを身近な人たちや次の世代にも分かってもらいたいので、派遣事業での経験や被爆者の方々の言葉をありのまま伝えていくという使命を果たしていこうと思います。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画人権課 人権文化交流担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9088 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。